
|
|
音円盤アーカイブス(2006年7,8月) この作品が、リリースされた1990年当時は今よりヨーロッパ盤は、結構値がはって、正規の卸で新譜で入荷しても3400円とか3300円とかそんな値段のものが多かったように記憶している。 月にかけられる限られた予算の範囲内で、どれにしようか絞り込む作業は、ジャズファンなら誰もが経験していることとは、思いますが楽しくもあり辛い作業であると言えるでしょう。 この作品など、「ライトハウス」のカタログで絶対良いだろうなと目を付けつつ、予算上泣く泣く振り落とした一枚。 来月買おうと伸ばすはいいが、来月は来月の必要盤が目一杯あるわけで、一度手元をすり抜けたブツを手に入れるのは結構大変なのですね。 後年いざ、買おうとしたら後悔、先に立たず、気がついたら入手困難で、なかなか手に入れることが出来なかった作品。 そんな一枚がようやく、再プレスされて、入手しやすくなりました。 と言っても、プレス枚数は限られているので、再び幻化する可能性が高いので。油断大敵です。 見つけたら入手されんことをお薦めいたします。 この作品は、RUDD BRINKのムーディーなテナーに魅力が集約されていると言ってよいでしょう。 こんなに趣味に良いテナーはそうそう、聴けるものではありません。 さらっとしているのだけど、深みがあってそれこそ人生の酸いも甘いもかみ分けた、大人のテナーサックスとは、こんな演奏を言うのだと思う。 ズートやゲッツを彷彿するほどの、歌心満開のプレイです。 ブリンクの場合、より親近感が湧くというか、日頃のアクセク、ギスギスした心の疲弊を親しい友人が慰め、励まし、元気付けてくれるというか、そんなより親しみのある暖かいものを感じるのですね。 ざらついた気分がベルベットのウォームテナーに洗い流されると言ったらよいだろうか・・・ PIM YACOBSのプレイに触れなかったですが、もちろん良いです。 「COME FLY WITH ME」は、皆さん持ってられると思いますが、この作品もヤコブの代表作だと思います。 全曲捨て曲なし、スタンダードがまるで彼らの演奏のために作曲されたのではないかと錯覚するくらいに、フィットしています。 メンバーはPIM JACOBS(p) RUDD BRINK(ts) WIM OVERGAAUW(g) RUDD YACOBS(b) 録音は1990年3月5,6日 STUDIO 44 MONSTER ,AMSTERDAM ---------------------------------------------------------  DAVE MACKAYと言えば、インパルスからジャケットも最高のブラジリアン・ジャズの隠れ名盤「DAVE & VICKEY」が有名ですが、本格的なジャズ作品としては、この作品だろう。 MAMA FOUNDATUIN第1弾としてリリースされたけど、リリース当時の1990年頃は見向きもされず店頭にいつまでも残っていた記憶があります。 今ほど当時はピアノトリオ熱は過熱していなかったのは、確かです。 この作品、職人が丹精込めてつくりあげた珠玉の作品という感じの一作に仕上がっています。 デイブ・マッケイのピアノは、表現が爆発することはなく、いわゆる天才的なプレイは聴かれない。 どちらかというと、地味なスタイルで、スタンドプレイのような派手な見せ技は駆使していないのですが、自分の中での律した範囲の中で最大限の振幅幅を伴った緩急自在のプレイを見せてくれています。 まさに、実直、質実剛健さが窺われる、職人技と言ったところか? アンディ・シンプキンスがその分、ソロでフューチャーされていて、ハイエンド・ジャズ・オーディオで聴けば、多分ボトムの最も低い「ブー-ン」と唸る弦の震える音や胴鳴りが聴けるのではないかと思う(ここは、聴感上の推測です。ルーファス・リードやレイ。ドラモンドの音に近いものを感じるので。)素晴らしいソロワークを披露していて、トリオとしてのエンターテイメント性を高めている。 ピアノトリオファンならずとも、手元に置いて折に触れて聴くたびに幸せを噛みしめることの出来るスルメ盤だと思います。 Dave Mackay(p) Andy Simpkins(b) Ralph Penland(ds) 1 Serenata (4:54) 2 Ev'ry Time We Say Goodbye (5:54) 3 Sometime Ago (6:42) 4 Django (9:16) 5 I Didn't Know About You (6:02) 6 Along Came Betty (6:53) 7 Thanks for the Memory (5:27) 8 Midnight Song for Thalia (5:45) 9 Children at Play (6:18) 10 Windows (6:23) 11 Alone Together (9:12) ----------------------------------------------------------  お医者さんでもある、アルトサックス奏者CHRIS STEWARTが2005年にリリースした、キャノンボール・アダレー賛歌集。 後でアップ致します。 と書いてから、今書き足しているのは日付が、22日になろうとしている時間なのだけど、この2日間、いつにもましてバタバタとしていて、ブログが後回しになってしまいました。 こういう作品を聴くと、いまだにジャズのメジャーリーグはアメリカなのだなと思ってしまいます。 語り口がネイティブなのである。 キャノンボール縁のこういうナンバーをいまどき、ゾロゾロと真っ直ぐど真ん中で演奏することに、多分わが国のミュージシャンだったら、照れが生じるのではないだろうか? レフトアローンを吹くのと同じように、ワークソングを正面切って大真面目に演奏することは、違和感を感じると言うか、照れくさいのではないかと思うのです。 アリゾナ州で活躍するクリス・スチュアートら5人は、そのプロジェクトに大真面目で望んで、それがまた、見事に決まっているのであります。 そんなことからも、やはり発祥の地というか,文化的遺産を引き継いでいく血という部分でも、こういうベタな企画物の場合に、その天然の部分が最も素直に出てくるのではないかと思うのだ。 彼らは、もちろん、アダレイやコルトレーンの役回りを演じているわけでなく、自身のスタイルでプレイしている。 とくに、変わったことをしているわけではなくて、自分の語り口で、真正面に曲を捉えてストレートに演奏している。 まるで、それで充分じゃないかと言わんばかりに・・・ 日本のレコード会社がつくるような企画作品との違って、自発的に作られたであろうこの作品は、そういう点でわざとらしさや、あざとさがなくて、ストレートに嫌味なく入ってくるのです。 メンバーはCHRIS STEWART(SS,AS) LUCAS PINO(TS) DAN DELANEY(P,ELP) CHRIS FINET(B.ELB) DOM MOIO(DS) 1. High Fly 2. Work Song 3. Sack O' Woe 4. Stars Fell on Alabama 5. Jive Samba 6. Dis Here 7. The Sidewalks of New York 8. Hamba Nami 9. Domination 10. Country Preacher 11. Medley: Walk Tall - Mercy, Mercy, Mercy 録音は2005年6月28日 TEMPE,ARIZONA ----------------------------------------------------------  現在NYで活躍中の新進テナー奏者、MICHAEL CAMPAGNAのデビュー作。 ベース、ドラムスがHans Glawischnig, Ari Hoenigなので、興味をもち、4月初めに注文をかけたのですが、その時は品切れで、ようやく先週入荷したのです。 マイケル・カンパーニャは、ハリウッドで生まれ、フロリダで育ったからなのか、志向しているサウンドは、ストレートアヘッドな現代ジャズといった趣があり、そこには、ブルックリン派のサウンドの要素も垣間見られるのであるが、あまり重苦しい感じがせず、どちらかと言うとカラッとした大陸的なおおらかさを感じさせる。 1曲目から、若者らしいフレッシュでスタイリッシュな曲が流れてきて自然と聴き耳を立てるようになるのだけど、全体の演奏を引き締めているのは、アリ・ホーニッグの力によるものだと思う。 演奏が良くなるも、悪くなるも最も責任が重いのはドラマーなのは、周知のことだとは、思うけどこういう演奏を聴くといまさらながら、それを実感いたします。 ナベサダが、昔、実の弟、渡辺文男をクビにしたことを聞いたことがあるけど、まんざら嘘ではないと思う。 リズムに最も厳しいサダオさんらしいエピソードだと思うのだ。 ピアノのROBERT RODRIGUEZもなんのインフォメーションもないので、どういう人物なのか分からないのだけど、音楽に色をつけるのが非常に上手いピアニストだと思います。 是非、この作品のリズムセクションで、ピアノトリオを聴いてみたい。 リーダーのカンパーニャは、そんな二人に比べるといささか分が悪いのであるけど、決して悪いテナー奏者ではないです。 個性という点ではまだまだこれからだけれども、リック・マ-ギッツァ~クリス・チークやシーマス・ブレイクあたりの白人現代テナー奏者の語法を体得した今からのミュージシャンだと思う。 表現の幅がより広がって、遊びや余裕の部分が出てくれば、もう一皮剥けた姿を見せてくれるのではないかと思うのだ。 今後に期待したい。 メンバーはMICHAEL CAMPAGNA(TS)MICHAEL RODRIGUEZ(TP)ROBERT RODRIGUEZ(P)HANS GLAWISCHNIG(B)ARI HOENIG(DS)SAMUEL TORRES(PER) 2004年6月2,3日 SYSTEM TWO STUDIOS, BROOKLYN, NY -------------------------------------------------------  今年、1月にFAT CATで演奏されたライブ作品で、入荷案内があると同時に、メンバーの顔ぶれに、期待が高まった。 いずれも、現代ジャズシーンにて、その名を馳せている存在が集ったセッションでどんな音が鳴っているのか? ここが一番の関心を引くところであるのには、違いない。 このメンバーなので、当然レギュラーグループではなく、このレコーディングの為に召集されたメンバーだと思うのですが、日常的に顔を合わせて、共演している仲だと思うので、違和感はない。 ただ、多少のリハーサルはあれど、オマール・アヴィタルの楽曲を完全にメンバーが消化しきっているかというと、そこは、多分にワンタイムパーフォーマンス的興行であるが故、時間的な制約があったのはいたしかたないところか? そんな背景のもとに、彼らの普段着の姿が結構でた、レコーディングなのかもしれない。 比較的厳かな雰囲気で、1,2曲目が過ぎていって、エルビン・ジョーンズに捧げた3曲目あたりから、俄然熱気を帯びてくる。 ガスバーナーのような、直接的熱さではなくて、じわじわと体の内面から温まってくる遠赤効果のような熱気。 楽曲の解釈は、メンバーそれぞれに任せられている部分が多分にあると思われ、各人が各々結構好き勝手に演っているように察せられるのですが、振幅の幅が楽曲の許容範囲の中でたくみにコントロールされているので、自身の持ち味をだしつつ、まとまった演奏に聴こえるのはその為だと思われる。 アーロンは自己のどのアルバムよりリラックスして弾いているし、ターナーは豪放と浮遊の間を行きつ戻りつ、ソロイストとしての対場を楽しんでいるようだし、アヴィシャイは、ジャージーなフレーズを連発。 で、全体の手綱をしっかり持って主導権を握っているのはリーダー、OMER AVITALその人とまさに、ベーシストらしい作品となった。 ミンガスほど、恐くはないと思うけど、ミンガスのように各人の自由度を尊重した上で、自身の音楽を演奏できるリーダーシップに長けた統率力のあるベーシストだと思う。 録音の線が細く、もう少し、前へ出てくる音で収録されていたらもっと迫力が出てよく聴こえたかもしれない。 メンバーはOMER AVITAL(B)MARK TURNER(TS)AVISHAI COHEN(TP)AARON GOLDBERG(P)ALI JACKSON(DS) 録音は2006年1月14,15日 FAT CAT NYC -----------------------------------------------------------  オーストラリアのRufus Recordsの作品は、昨年の秋、苦労して個人輸入して、このBERNIE McGANNも2種類ほど、仕入れて結構好評だったのを覚えている。 今回、国内卸元からの配給が決まりこれで、前より仕入れしやすくなりました。 オーストラリアのジャズシーンは、結構わが国ではまだまだ知られていない未知の部分が多く、 音楽性も正統派からボーカル、フリーまでそれぞれが結構盛んで多様性に富んでいるので今からあれこれと探索してみるのも面白いかもしれない。 意外に、ピアノトリオは不人気なのか作品数が少ないのも特徴。 この作品は、McGANNの2005年最新作で、ピアノレスのトランペットとのカルテット作品となっています。 ASとTPのピアノカルテットというと、歴史的なオーネット・コールマンのカルテットを誰でも直ぐに思い浮かべると思うけれども、このバーニーのカルテットも、ピアノというコード楽器の呪縛から解放され、同じ楽器編成となると、自然とそのサウンドが似てくるのは致し方ないところか? BERNIE McGANNは、マクリーンのようなファナティックな吹き方も出来るし、コニッツのような、クールで、浮遊感溢れる波乗り気分のサウンドも発することが出来る器用なサックス奏者。 オーストラリアでは、ダントツの実績があるアルトサックスの重鎮であります。 McGANNが素晴らしいと思うところは、そういう現在の自分の位置づけに、安穏とすることなく、こういうジャズスピリット溢れるスリリングな音楽に、トライし続けているところだと思う。 この作品もセールス的にはあまり期待できないかもしれないけれども、分かってもらえる方には、分かってもらえると思う。 ラスト曲のドライでビタースイートな艶やかなアルトの音色には痺れます。 メンバーはBERNIE McGANN(AS)WARWICK ALDER(TP)LLOYD SWANTON(B)JOHN POCHEE(DS) 録音は2005年6月20-22日 EAST SYDNEY --------------------------------------------------------  サンフランシスコ・ベイエリア地区で活躍している無名のテナーサックス奏者の2004年ワンホーンアルバム。 ウェイン・ショーター曲を2曲(LESTER LEST TOWNとINFANT EYES)を演奏しているのでどれ、仕入れてみようという気になった。 アルバム自体は、二つのセッションから構成されていて、クレジットをみて気がついたのだけど、PAUL NAGELとART HIRAHARAがピアノを弾いている。 ここで、少し打ち明け話を少しいたしましよう。 こういう玉石混交の自主制作の作品で、ワンホーンものの作品の玉を見つけ出すのは、ピアノトリオの作品に比べて、至難の業なのです。 ピアノトリオというフォーマットは、現代のジャズシーンにおいて、最もハードルが低いと言うと語弊があるけど、リズムがしっかりしていて、ピアニストが最低限のテクニックを持ち合わせていれば、そこそこ、良いように聴こえるものなのです。 ピアノという楽器そのものの潜在的な表現能力によることも、あると思う。 聴感上、心地よく聴こえ、それに伴うメッセージも、すんなりと入ってきて、オーディオ的にも、最もシンプルかつ奥行きの深いところまで追求できる醍醐味を持ち合わせている、ピアノトリオのアルバムが90年代以降、加速度的にリリース、まさに百花繚乱の体をなしているのも、当然といえば当然なのである。 それに比べ、直接的な肉体的運動量、つまりテナーサックスやトランペットなどのホーン物の場合、ジャズジャイアンツや名前の通っている大物連中に比べ、比較する尺度が、ピアノトリオに比べたら辛くなるのでないかと、常日頃思っているのだ。 これは、全くの個人的意見で、独断と偏見なのかもしれないけれども、ピアニストの活躍ぶりに比べて、どうしてもマイナーな他の楽器のローカルミュージシャンの作品は人気の面で劣るのは、厳然たる事実なのです。 実際のライブシーンでは、全く違うのだけど・・・ ビジネス面でピアノトリオがどんどん売れていくことは、実に有難いことなのだけど、もっといろんなところに目を向けてもらいたいというのが本音のところなのです。 いままで、何社かのレコード会社がそういう経緯もあり、ピアノトリオの次に来るものとしてワンホーンものシリーズを企画するという動きが見られたけど、なかなか機動に乗るのは難しいようで、長続きしていないのが実情ではないかと思うのです。 ピアノトリオのファンの何割かが、そういうワンホーンものや他のコンボもの、ボーカルにも目を向けてくれれば、ジャズ界(この場合、レコード業界から小売業界になるか)自体の活性化に繋がると思うのだけれども。 その為には、聴くに堪える良い作品を制作、紹介していく努力が必要なことは言うまでもないのですが・・・ この作品など、玉の部類に入る方だと思う。 これから、マイナーピアノトリオはもちろん追いかけていきますが、こういう知られざるワンホーンものの仕入れを少し増やしていこうかなと思っている次第です。 メンバーはJIM GRANTHAM(TS,SS)ART HIRAHARA(P)FRED RANDOLPH(B)STEVE ROBERTSON(DS) PAUL NAGEL(P)JOHN SHIFFLETT(B)DAVE ROKEACH(DS) 2004年作品 ------------------------------------------------------------  PAOLO DI SABATINOの2001年作で、昨年レア本で紹介以来、わが国でも俄然ブレーク、HALLAWAYレーベルの作品や、トリオ作品にも注目が集まった。 ピアノトリオと、STEFANO DI BATTISTA(AS),JAVIER GIROTTO(SS),DANIELE SCANNAPIECO(TS)、現在では、各々がイタリアを代表するサックス奏者になったと言える3人のサックス奏者がフューチャーされた演奏が聴ける。 全曲オリジナルで勝負した力作なのが、アルバムを聴き始めると直ぐに分かる仕掛け。 イタリアのラテン的明るさといっては、端的な表現過ぎるかもしれないけれども、燦々と太陽が降り注ぐ南イタリアの情景が浮かんでくるような、カラッとした、それでいてどこか懐かしさを感じさせる楽曲を、フューチャーされたサックス奏者がパッショネートに吹き上げるナンバーやパオロの爽やかさを感じさせるスムースで快活なソロは、実に聴き応えがあるのです。 作曲と演奏両面のバランスがとても良いミュージシャンだと思う。 個人的なベストはJAVIER GIROTTOのソプラノがフューチャーされる「RUA ALAGOINHAS 301」と4曲目ピアノトリオの演奏「I CAN TOUCH THE STRAS」。 他にも良曲がたくさんあって、聴く人によってベスト曲は変わると思うけれども、どれもが魅力的な演奏、楽曲で聴く人を選ばない、万人が聴いて満足していただけるアルバムではないかと思うのだ。 メンバーは、Paolo Di Sabatino(P)Stefano Di Battista(as,ss)Javier Girotto:(ss) Daniele Scannapieco(ts)Carlitos Puerto(b,elb)Horacio "El Negro" Hernandez(ds) 1. The Country Lane 2. Rua Alagoinhas 301 3. Kenny 4. I Can Touch the Stars 5. Another Short Breath 6. A New Toy 7. Another Step 8. Fine della Storia 9. You Can Dance Now 10. A Little Song for Carlitos 11. UB's Mood 12. Dreamy Eyes 13. Open Sea 14. Uno sguardo tra gli angeli 録音は2001年3月23-25日 TERAMO,ITALY -----------------------------------------------------------  現代ジャズをずっと追いかけている方ならば、数年前発売されて評判になったTHE NAIROBI TRIOという、中身は活きの良い、二管編成ハードバップアルバムのことを覚えていないだろうか? そう、この作品は、そのナイロビ トリオの3枚目のアルバムのあたるものなのです。 三枚目にして初のライブ作品となっています。 フロント陣は1作目のANDY SUZUKI,STEVE HUFFSTETERから、前作から、現メンバーのKYE PALMER,CHUCK MANNINGに交代しています。 最初のメンバーより知名度はより低くなりましたが、肝心のプレイは勝るとも劣らぬ力量の持ち主で、両者とも骨のあるまさに、ハードバップど真ん中のプレイをしてくれています。 特に、鋭角的に切り込んでくるパルマーのトランペットは、少しリー・モーガンを彷彿させるとっぽさと不良性を感じさせるもので、テクニシャンなのだけど優等生のトランペッターが多い中、こういうタイプのトランペッターはかえって新鮮に感じます。 リズムセクションは、不動のメンバーで、躍動感に溢れた活気ある演奏マナーは、聴いていてスカッとすること間違いなし。 作り物の急造コンボやレコーディングの為のセッションでは、決して味わえることができない一体感、グルーブ感は、まさに長年レギュラーグループとして活動してきた賜物だといえるでしょう。 特筆できることは、彼らのエンターテイメント精神溢れた演奏マナーです。 この道何十年のベテランファンが聴いても、最近ジャズを聴き始めた初心者が聴いても、「JAZZってほんとにいいなぁ」と思わせる。 これって、簡単なようで、周りを見渡すとそういうジャズって意外と少ないのが分かる。 一度、DMQの演奏を聴いてみてください。 Chuck Manning(ts) Kye Palmer(tp) Curtis Brengle(p) Jeff Donavan(ds) Larry Muradian(b) 1. Black Nile 2. Whisper Not 3. It's You Or No One 4. Edda 5. Softly As In A Morning Sunrise 6. Stella By Starlight 7. Locomotion 録音は2006年9月2日 Cafe322,CA -----------------------------------------------------------  実はこの作品の存在を知ってまだ一日も経過していない。 正確には昨日深夜、ブログ仲間のポーランドジャズに精通しているオラシオさんのブログを拝見して、知りレーベルサイトで少し試聴してみて、ビビッときたのです。 「これは当たりだな。」と、直感的に思った。 直ぐに、ポーランドのbcd RECORDSにTEL、こういう場合、時差はありがたい。 輸出担当のものを、電話口に呼んでもらう。 英語とポーランド語をなんとか駆使しながら何とか交渉開始。 要は「直ぐに送れ」と・・・。 というのは、真っ赤な嘘で、翌日(つまり今日)、都内某所にTEL。 「1ヶ月かからないうちに入荷しますよ。」とのこと。 ヘルゲ・リエンやボボ・ステンソン、エンリコのファンはもちろん、シンプル・アコースティック・トリオのファンの方なんかに、まさにジャズトフィットするかもしれません。 水晶の光のような輝きを放つ知られざる東欧のピアノトリオ盤にご期待下さい! Przemyslaw Raminiak(p) Maciej Garbowski(b) Krzysztof Gradziuk(ds) Straight Story (P.Raminiak, M.Garbowski) 7:09 Eposs (M.Garbowski) 8:39 Psalm I (P.Raminiak, M.Garbowski, K.Gradziuk) 3:09 Wait (P.Raminiak, M.Garbowski, K.Gradziuk) 0:30 Frozen People (P.Raminiak, M.Garbowski, K.Gradziuk) 8:32 Sange (M.Garbowski) 5:15 No One Knew (P.Raminiak) 9:09 Psalm II (P.Raminiak, M.Garbowski, K.Gradziuk) 4:00 Nordic Storm (P.Raminiak, M.Garbowski, K.Gradziuk) 5:21 Innocence (P.Raminiak, M.Garbowski, K.Gradziuk) 3:53 --------------------------------------------------------  「SOME SOUL FOOD」が大好評で受け入れられたアラン・ミオンが、1992年NYで、マーク・ジョンソンやトム・レイニーらと録音した作品。 「SOME SOUL FOOD」盤を気に入ってもらった方には、(他の方のブログでこの作品が取り上げられているのを見ても、まず悪評を見ることはない。お買いになったほとんどの方に満足して頂いている作品だと思います。)安心してお買い上げ下さいと言っておきましょう。 基本的に作品のテイストが同じなので、間違いないと思います。 このアルバムでは、本人がフランス語で2曲ばかり歌っているのですが、作品すべて歌詞をつけて口ずさみたくなるほど、メロディアスなものが多く魅力的です。 決して難しい曲は作らないのだけど、一度二度ではなかなか覚えられない。 しかし、メロディーの心地よさは脳裏にしっかりと焼きついているので、確かめたくて三度、四度と繰り返し聴きたくなるといった寸法である。 ただスイートなだけではなくて、ほろ苦さや酸っぱさなど、楽曲それぞれのテイストも微妙に異なるのでアルバム一枚を何回リピートしても飽きないのです。 楽曲の事ばかり書いてしまったけど、演奏が申し分ないことは、SOME SOUL盤を聴いてもらっている方には言うまでもないと思う。 「SOME SOUL FOOD 」と「IN NEW YORK」この2枚の作品で、どうやらアラン・ミオンは、忘れることの出来ないピアニストとなったようだ。 Alain Mion(p,vo) Marc Johnson(b) Tom Rainey(ds) David Binney(as) 1 Montse 2 Levallois 3 Dolphin Game 4 Yellow Cab Nite Blues 5 Jean 6 Tivoli 7 Un Gospel Pour Dexter 8 Stand Away 9 Godfather 10 One More Blues 11 Coming Back 1992年5月4,5日 NY David Baker録音 ------------------------------------------------------------ 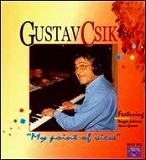 ハンガリーのピアニスト、GUSTAV CSIK(グスタフ・チク)の1998年録音ピアノトリオ作品。 ジャケットのつくりがジャズのアルバムにしては、珍しく凝っています。 1曲目のプレイボタンを押すと同時に、活気あるパワー系のアクションプレイが聴かれ、このピアニストがテクニシャンだということが分かる。 アップテンポの曲で、縦横無尽に鍵盤上を早弾きで駆け巡る様は、ダイナミック感にも溢れていて 隠れた名手ぶりを発揮しているといえます。 ドラムのアルヴィン・クイーンのテキパキとがっつり叩き込まれるリズムも、スタイル的には決して新しいとは言えないけれども、気持ちの良いもの。 GUSTAVはアップテンポの人だけではない。 2曲目「FOR ISABEL」や「クリフォードの想い出」などの、バラードナンバーにおいても、感情過多になり過ぎない、「さりげない」とか「そこはかとない」とかいう言葉がふさわしい、抑制された感情表現が、秀逸。 個人的ベストはO・ピーターソンの「BOSSA BIGUINE」に決まり。 アップでもスローでも、先程の言葉を裏返せば、クールな表情を持つGUSTAVが、この曲では、顔を紅潮させ、曲にのめり込んでいる様が目に浮かぶ。 いつもは、クールなグスタフが演奏しながら笑みを浮かべているような、光景が思い浮かぶのだ。 この曲だけ異色、そして名演。 メンバーはGUSTAV CSIK(P)REGGIE JOHNSON(B)ALVIN QUEEN(DS) 1 We Are Here 2 7+7+9-3 for Isabel 3 Billie's Bounce 4 Anthropology 5 I Remember Clifford 6 Bossa Biguine 7 Ellington, Duke Meadley: Melancholy/What Am I Here For 8 Caravan 9 Very Early 1998年7月録音 -----------------------------------------------------------  1983年イスラエル生まれのギタリスト、GILAD HEKSELMANが、NYの「FAT CAT」で録音したデビュー作品。 JOE MARTINとARI HOENIGが脇を固めた鉄壁の布陣になっているので、思う存分自身の音楽性を披露できる次第。 速弾きに頼らない(超絶技巧の高速プレイがそれはそれで、ギターの場合、快感なのでありますが)サウンド志向の高いギタリストなのが、聴きだして1,2曲で分かる。 フレーズもオリジナルなものを感じるし、緩急メリハリのつけかたが素晴らしく、注目に価するギタリストだと思う。 そして、このライブ作品では、やはりARI HOENIGのドラムがカッコいいです。 2曲目など、思わずそのプレイに聴きほれてしまいます。 スタンダードナンバーになると、特にバラード曲ではジム・ホールの影響が感じられるけれども、 GILADの場合、ホールからの直接的影響だけではなくて、ホールチルドレンともいうべき、現代ジャズギターのグレイツ、パット・メセニーやジョン・アバクロンビー、ジョン・スコやビル・フリゼルなんかの片鱗をちょっとしたフレーズの端々に感じられる気がしないでもない。 まだまだこれから個性に磨きをいくところも多いと思うけれども、自身の歌い方、語り口を身に着けている発展途上の状態ではあるけれども、ポテンシャルに期待できそうなギタリストが登場したと思う。 ジョン・スコフィールドが70年代のジャズシーンに登場した時のような、ユニークさの片鱗を匂わせる今後も注目していきたいギタリストです。 メンバーはGILAD HEKSELMAN(G)JOE MARTIN(B)ARI HOENIG(DS) 1 Purim (Hekselman) 2 Hello Who Is It? (Hekselman) 3 My Ideal (Robin/Whiting) 4 I Fall in Love Too Easily (Styne/Cahn) 5 Suite For Sweets (Hekselman) 6 When Will the Blues Leave (Coleman) 7 The Summer of Laughs and Tears (Hekselman) 8 Breathless (Hekselman) 9 I Should Care (Cahn) 10 My Second Childhood (Caspi) 録音は2006年3月13,14日 FAT CAT, NYC ----------------------------------------------------------  ノルウェーの爆音轟音系ジャズグループ、JAZZMOBの第3作目、JAZZAWAYレーベルからは、2作目となる。 JAZZMOBほど、JAZZAWAYのレーベルカラーとぴったりとフィットするグループもないのではなかろうか? 喧騒感のある、分厚く熱狂的でありながら、耳馴染みがよいテーマ合奏を経て、各人のアドリブが縦横無尽に展開される。 インからアウト、調性からフリーへ自由に出入りするアドリブマナーは、一聴60年代フリーを連想させるが、彼らのサウンドにはどろどろとした情念とかブラックナショナリズムとかいうものは、当然のごとく感じられない。、(時代背景、民族性) サウンドモデルとして下敷きにしているところは勿論あるのだろうけど、それ以降のジャズ、ロックを俯瞰、消化したうえでの60年代フリージャズのマナーをテイストとしてうまく使っていると思うのだ。 実際、聴いてみれば分かるけど、そんなに無調になっている部分はなくて、それでいてある種の呪縛性、酩酊感、祝祭性などフリーを聴いた時のような気分を味わえる部分があるのだ。 彼らのサウンドが、行き当たりばったりの出たとこ勝負ではなくて、結構戦略的に、そういうサウンドを取り入れて音つくりをしているのではないかと思うのだ。 そして、わだかまりやこだわりというものがないので、風通しがよい。 平たい言葉で言えば、あっけらかんとしているのだ。 こういうところが、現代の若者に、(他人とは差別化したサウンドを追い求めている?)受けているのではないかと思うのだ。 メンバーはJON KLETTE(AS)GISIE JOHANSEN(TS)KARE NYMARK(TP)ANDERS AARUM(P,ELP)PER ZANUSSI(B)ANDEAS BYE(DS,PER) 2005年12月7,8日18日 ----------------------------------------------------------  1997年録音、2000年にBROWNSTONE からリリースされた前作は、ニューヨークの日常的ハードバップサウンドがする、中々の好内容だったが、録音自体はあれからすでに10年ちかく経過しているので、リーダーアルバムとしては久々のものとなる。 今作には、ロニー・キューバーや最近惜しくも亡くなったジョン・ヒックスが参加。 前作にも参加のテナーのGEORGE ALLGAIERが引き続き参加しており、テナー、バリトンというあまり組み合わせのない、2管編成のクインテット作品となっています。 キューバーもアルゲイヤーも、1曲目からフルスロットルの吹きっぷりで、バフバフ、ブリブリという擬音がぴったりな、サックスバトルは、聴いていてスカッとする。 NYのジャズシーンというと、ブルックリン派やアンダーグラウンド派などの先進先鋭組の近況や、ヴィレッジヴァンガードやブルーノート、リンカーンセンターなどのエスタブリッシュメントの情報がどうしても先行してしまうが、ジャズクラブやライブハウス以外の、レストラン、ショーパブ、キャバレーなど様々な場所で演奏されている。 そんなところで、最も普段着の、肩肘張らない、等身大の演奏がされているといってよいのかもしれない。 PAUL BRUSGERのこのアルバムを聴いて、ふとそんなことを感じている。 同じハードバップ系レーベルでも、HIGHNOTEやSHARPNINE、ましてや大手レコード会社(最近はリリースされることもあまりないと思うけど)からの作品に比べて、ミュージシャンのリラックスした姿が記録されているような気がしてならない。 手抜きをしているわけではなくて、演りたいように演っている姿が、脚色なしに、それこそNYの名も知れぬ小さなジャズクラブで聴いているような雰囲気が味わえるような気がしてならない。 CAP(CONSOLIDATED ARTISTS PRODUCTIONS)やなくなってしまったけどBROWNSTONE,UPTOWNなどのハードバップ系レーベルは、まさに、そういう家内制手工業的カスタムメイド感覚の作風が多くて悪くない。 決して名盤ないのだけど、親しみやすく、気の置けない友人のような存在の作品が多いのだ。 メンバーはRONNIE CUBER(BS)GEORGE ALIGAIER(TS)JOHN HICKS(P)PAUL BRUSGER(B)JOHN JENKINS(DS) 録音は2002年11月26日 SYSTEM TWO STUDIOS, BROOKLYN -------------------------------------------------------  さらさらの黒髪に、澄み切ったつぶらな瞳、情熱的であることを想像させる厚めの唇・・・ YVONNE SANCHEZ(イボンヌ・サンチェス)は、ポーランドとキューバの血を引いたジャズ歌手で、現在チェコの首都、プラハで活躍している。 甘酸っぱい爽やかさを感じさせる歌手だと思う。 ほろ苦さを若干感じさせる甘さは、食べ物に例えれば、マーマレードの味か? 4曲目「Feitico de Irena」などまさに、そういう感じがするのです。 この曲など、南米らしい情熱的なエモーションを感じさせる曲調なのだけど、彼女の場合、それを全面的に押し出すのではなくて、東欧らしいクールネスな表現を巧みに織り交ぜていてそのあたりがとても新鮮に聴こえるのですね。 最近、トリオによる新作をリリースしたロベルト・バルザール・トリオとの息もぴったりで全13曲を最後まで一気に聴かせる実力は、さすが数ヶ月でチェコのジャズシーンで認められただけのことはある。 Yvonne Sanchez(vo) Stanislav Mcaha(p) Robert Balzar(b) Jiri Slavicek(ds) Guest;Filip Jelinek(tb) Radek Zapadlo(ts) Ernesto Chuecos(g) 録音は2002年1月 Prague 1 Old Devil Moon 2 Way You Look Tonight 3 In a Mellow Tone 4 Feitico de Irena 5 My Romance 6 Invitation 7 Nica's Dream 8 All of Me 9 I'll Remember April 10 Lover Man 11 Well You Needn't 12 Dindi 13 Autumn Leaves ----------------------------------------------------------- 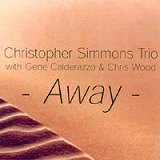 NYのピアニスト、CHRISTOPHER SIMMONS(クリストファー・シモンズ)がジョーイ・カルデラッツォの兄弟、ジーン・カルデラッツォ、Medeski, Martin & Woodのベーシスト、クリス・ウッドと1992年に録音した作品。 後になってCD-Rでリリースされた作品のようで、収録時間が30分あまりで、60分超えの作品に慣れ親しんだ耳には少し短い気がしないでもないのですが、ミニアルバムだと思えば良いのでしょうか? クリストファーのピアノはジョン・ルイスのような所謂省エネ型ピアニストに属すると思う。 右手と左手を一生懸命動かして、音符でにぎやかしく埋め尽くすことに、切磋琢磨しているピアニストが多い中、ポロン、ポロンと(実際はそうでもないのだが、ここでは対比的な意味合いで)優雅に鍵盤に指を置いていくクリストファーのスタイルは、かえって新鮮に聴こえるかもしれません。 テクニックがないわけではないと思われ、意識してそういうスタイルに専念していると思われる。 そんな、演奏スタイルと曲想が最もマッチした1曲が、ビル・エヴァンスの「INTERPLAY」。 単音中心のクリストファーのピアノと、うら寂しい曲調が見事にフィットしていて、その反面リズムセクションは結構、カルデラッツォ、ウッズとも積極化果敢なアクティブなプレイを押し出していて、その対比具合が面白い。 MM&Wのクリス・ウッドも92年当時はこんな正統派もピアノトリオ演奏をしていたのが、分かって興味深い。 メンバーはCHRISTOPHER SIMMONS(P)CHRIS WOODS(B)GENE CALDERAZZO(DS) 録音は1992年8月 BROOKLYN, NY -----------------------------------------------------------  一昨日、ショップのほうのブログ、「VENTO AZULの店長日記」のほうに書いたものなのだけど、 やっぱりより多くの方に情報を流しておいたほうが良いと思い、こちらのほうにも転載ね。 今日、送られてきました。 感動で、涙ちょちょぎれてます。 既に、今日5回目の鑑賞です! この作品、LP時代に自主制作で、再プレスがされなかったこともあり幻化していた作品。 リリース当時から、その素晴らしさは、通には知れ渡っていて、皆入手するのに躍起になっていたほどだ。 学生当時の行きつけのジャズ喫茶「JOKE」でよく聴いたのを思い出す。 今回、セントジェームス30周年記念として、初CD化されることを、知ったのが、丁度今度発売されるジャズ批評に田中さんの最新アルバム「残月」を取り上げさせてもらおうのに、一応お断りしておこうと思い「St,James」のHPを久しぶりに(たぶん2,3年ぶりに)覗いた時の事。 何かの力がこのアルバムとの再会を取り持ってくれたような気がしてならない。 多分、あの時にHPを覗かなければ、そもそもジャズ批評に最初はリストアップしていなかった田中さんの作品を急遽取り上げたくならなければ、復刻されたこと自体も知らずに時が過ぎ去ったのかもしれないからだ。 今回の復刻も、大手レコード会社からの復刻ではなくて、セントジェームス自体の復刻作業のようで、直ぐに完売、再び幻化することは、目に見えている。 たぶん、一般の小売販売はないだろうから、手に入れたい方は直ぐにセントジェームスに、メールするか、TELされるべし。 日本のジャズ、ピアノトリオの金字塔の一枚です。 メンバーは田中武久(P)中山良一(B)東原力哉(DS) 問い合わせ先は 田中武久さんの店 セントジェームスへ、 -----------------------------------------------------------  TELARC移籍第1弾のこのアルバム、前作のレビュー(このブログの2004年8月だったかな?)の時に 豪華なつくりに満足しながらも、飾らない普段着のホーザのアルバムもまた、聴いてみたいと書いたのを覚えているのだけど、この作品、私のその欲求にまさにジャズトフィットした1枚となった。 全編、弾き語りのアルバム。 まさに「スカートをはいたジョアン・ジルベルト」の異名を持つホーザの本領が100%発揮されたアルバムとなったようだ。 たった一人のアルバムということもあり、彼女最大の魅力である、「声」に標準がフォーカスされている。 彼女が何かメロディーを口ずさめば、レストランのメニューや新聞の三面記事であろうと、たちどころに音楽となってしまうのではないかと、思わずにはいられないほど、まさに唄うために生まれたきたとしか言い様がないほど、天性の魅力的な声が、このアルバムにはたっぷりと詰まっているのです。 個人的には4曲目「ATE UEM SABE」が最も気にいってます。 晩夏の誰もいない海で、一人聴きたい気分です。 1 Duas Contas 2 Eu Nao Existo Sem Voce 3 Sutilezas 4 Ate Quem Sabe 5 Olhos Nos Olhos 6 Sentado A Beira Do Caminho 7 Molambo 8 Jardim 9 Demasiado Blue 10 Desilusion 11 Edredon De Seda 12 Nao Sei O Que Acontece 13 Detalhe 14 Fusion 15 Inverno ROSA PASSOS(VO.G) 2006年作品 -------------------------------------------------------- 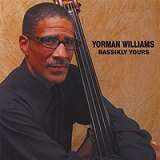 YORMAN WILLIAMSはハワイで活躍しているベーシストで、ハワイというとそのものズバリ音楽的にはハワイアンミュージックが伝統的な音楽として圧倒的なシェアを占めるのかもしれないけど、もちろんジャズも日常的に様々な場所で演奏されている。 もう20年前になるけれど、ウィントン・マルサリスが「スタンダードタイム」を録音した時、新結成したばかりのカルテットを偶然観たのは、オアフ島のホテルのバーラウンジだった。 本土から名の知れたミュージシャンが渡ってくるのだけど、その時に観たウィントンも、いつもより幾分リラックスした雰囲気で、それまでのウィントンのイメージを覆すものだったのを覚えている。 ハワイの気候と自然がミュージシャンを開放的な気分にさせるのだろうか、普段よりのんびりと聴こえる気がするのだ。 ヨーマン・ウィリアムスは、ベーシストということもあって、ケニー・バレルなんかが単身渡ってきた時はステージを共にするらしい。 ハワイにはブルース・ハマダというベーシストがいるけれど(今年、富士通ジャズフェスティバルで来日)ヨーマンのジャズも、オールドといってよいくらい(これは否定的な意味ではない)朴訥とした暖かく真っ直ぐにスイングするジャズだ。 カルテットは超有名ナンバーを、ストレートに演奏、難しい仕掛けやアレンジは一切なし。 ハワイのような気候のもとでは、あまり難しいジャズは似合わない。 だから、これが彼らのありのままの姿なのだろうし、つくったところがないので、音楽に嘘がない。 たまには、こういう超がつくくらいオーソドックスな演奏もいいものです。 人によっては駄盤の烙印を押すひともいよう。 駄盤、結構じゃないですか、駄盤には駄盤なりに良いところがどこかあるもの・・・ 駄盤を聴いてこそ、名盤の孤高さ、ありがたみが分かろうというもの。 名盤や有名作、本に掲載されているようなものだけを聴いているだけでは、分からないところがあるのですよ。 傑作とは間違っても言えないが、こんなのを軽く流しながら一杯飲る余裕がほしいですね。 メンバーはYORMAN WILLIAMS(B)DALE ALEXANDER(P)PAUL KRYBEC(DS)KEITH FAIRMONT(TS) 1. Take the A Train 2. Autum Leaves 3. Mood Indigo 4. What a Wonderful World 5. Night and Day 6. Body and Soul 7. Tenderly 8. Things Ain't What They Used to Be 9. Green Dolphin Street 10. Stardust 2006年作品 -----------------------------------------------------------  BILLY HARTの久々の新作で、おまけにマーク・ターナーのワンホーンカルテットということで、知り合いのショップさんに頼んで分けてもらいました。 ジャケットがいいですねぇ。 音が聴こえてきそうなショットです。 このメンバーなので、普通の4ビート演奏ではないだろうと思っていましたが、予想通り一捻りも二捻りもしているポストモダンな音作り。 ハート自身の演奏も、数年前に持病のことを知り、70年代の切れ味が失われてしまった原因が分かったのだけれど、この作品では、以前と違ったドラミングを体得したように私には聴こえる。 シャープネスを欠いた頃のハートのドラムは、スネアのタイミングやリズムが、妙に鼻につき音的には決して大きい音ではないのだけど、ハートの時代も終わったのかなと思っていた。 ところが、このアルバムでは、見事に復調したドラミングが聴けるのです。 現在の自分の体力にあった新しいドラミングに開眼したような、(実際基本的なところは、変わっていないのだろうけど、その辺りはnaryさんの専門的分析を待つことにしよう。)マーク・ターナーやアイヴァーソンのプレイとジャストフィットしたドラミングを聴かせているのだ。 以前のハートだったら、一人ちぐはぐな演奏に聴こえたに違いない。 ここでは、若手のメンバーと同世代のようなクッション性に富んだ柔軟なドラミングを展開。 ストレートなスイングする演奏ではないので、繰り返し繰り返し聴いてみて欲しい。 メンバー全員の高度な音楽性が、じわじわと遠赤効果のように、ハートに響いてくるはずだから。 このアルバム、ハートの再出発的なアルバムとなるような気がしてならない。 メンバーはBILLY HART(DS)MARK TURNER(TS)ETHAN IVERSON(P)BEN STREET(B) 2005年10月14,15日録音 Connecticut ----------------------------------------------------------  ほんのりと甘く鼻腔をくすぐり、口に含むと爽やかな発泡性とまろやかさでたちどころに桃源郷の世界へ連れ込んでくれる上質なシャンパンを飲んだ時のようなピアノトリオです。 ドゥミ・セックからセックぐらいの糖度か? すっきりした甘さなので、嫌味は全くなくて何回も聴いてみたく(飲みたく)なるような匙加減なのだ。 この時点でこの作品の成功は決まったようなものだろう。 シャンソンやフレンチポップスの名曲(耳馴染みの曲が多いです。)を題材にしているので、感情を込めすぎると、ベタになりすぎることを心得ていて、そのあたりのメロディーの輪郭を濃淡メリハリをつけて実に上手く料理しています。 原曲(素材)の良さを見事に生かして、オリジナルな解釈を過不足なく付け加えて、新たな一品を生みだす。 そういう意味でチャールス・ルーズは名シェフだと言える。 前菜から始まり、デザートまでまさに、とろけそうな甘美で美味な一作となりました。 この作品は、長い間メーカー切れしておりましたが、久々の再プレスとなったので、これを機会に入手されていない方は聴いてみてはいかがだろうか? Charles Loos(p) Bas Cooijmans(b) Bruno Castellucci(ds) 1 インディアン・サマー 2 ジャヴァネーズ 3 ロレット 4 さよならを教えて 5 私の隣人 6 黒い鷲 7 仲間を先に 8 懐かしき恋人たちの歌 9 私のお気に入り 10 双眼鏡の歌 11 いつかわかるだろう 2003年作品 ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
|
||